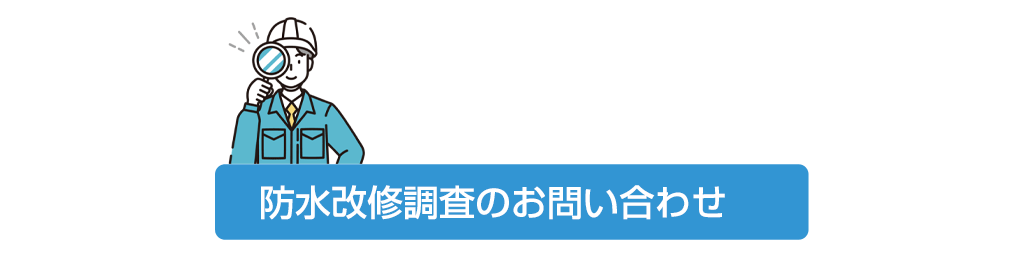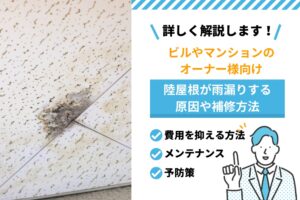ウレタン防水の膨れは補修できる|原因や放置するリスク・DIYの危険性を解説

所有マンション屋上のウレタン防水にできたプクプクとした膨れについて「どのように補修したら良いのだろう」「そもそも原因は何だろう」と気にされている方も多いのではないでしょうか。
見た目はすぐに破れそうになくても、放置すると雨漏りや修理費用の増加につながる可能性があります。
この記事では、ウレタン防水が膨れる原因・放置するリスク・膨れを予防する方法について解説します。
DIYの危険性や信頼できる専門業者の見分け方も紹介しますので、大切な資産を守るためにぜひ最後までごらんください。
・ウレタン防水が膨れる原因は下地からの湿気・防水層の劣化・施工不良などが考えられ、原因を特定しないと適切な補修はできません。
・DIYでの補修は原因特定や材料選定が難しく、被害を拡大させるおそれがあるため、防水専門業者への相談がおすすめです。
Contents
ウレタン防水の膨れは「早めに補修」が大切|放置するリスクとは

所有物件の屋上でウレタン防水に膨れを見つけた場合、すぐに破れそうでなくても安心はできません。
膨れは防水層に異常があるサインであり、建物を守るためには早期対応が必要です。
膨れは防水機能低下のサイン
ウレタン防水の膨れは、防水層が下地から浮いている状態です。
これは、防水層と下地の間に水分や空気が入り込んでいることを意味します。
正常な防水層は下地に接着していますが、膨れがある部分は接着性が失われ、防水機能が低下しているサインです。
小さな膨れでも、防水性能が弱まっていることに変わりはありません。
膨れを放置するリスク|雨漏り・高額な修繕費など
ウレタン防水の膨れを放置すると、雨漏りなどのリスクが生じる可能性があります。
施工直後のウレタン防水はゴムのような弾力があるため、膨れている箇所もすぐには破れにくい状態です。
しかし、紫外線などの影響で時間の経過とともに劣化が進むと、防水層は弾力を失い硬くなっていきます。
硬化した防水層はもろく、膨れた部分が破れやすくなるため注意が必要です。
防水層が破れると、そこから雨水が侵入して雨漏りの原因となります。
建物の資産価値を守るためにも、膨れの段階で対処しましょう。
ウレタン防水が膨れる原因|湿気・劣化など

適切にウレタン防水の膨れを補修するためには、まず原因を特定することが不可欠です。
主な原因として、以下の3点が挙げられます。
- 下地からの湿気や水分
- 防水層の破損・劣化による雨水の侵入
- 下地処理不足などの施工ミス
下地からの湿気や水分
コンクリートなどの下地に含まれる水分が原因となるケースです。
施工時に下地が十分に乾燥していないと、太陽熱などで温められた際に水分が蒸発しようとします。
この水蒸気が防水層を下から押し上げることで、膨れが発生します。
湿度の高い時期や雨上がりの施工では、下地の乾燥状態に注意が必要です。
防水層の破損・劣化による雨水の侵入
防水層そのものに問題がある場合も、膨れの原因となります。
経年劣化によるひび割れや、飛来物などによる傷があると、そこから雨水が防水層の下に侵入します。
侵入した水が下地との間に溜まり、温度変化によって蒸発・膨張することで、防水層が押し上げられて膨れとなります。
定期的な点検で防水層の状態を確認し、劣化が見られたら早めに補修することが、膨れの発生予防に有効です。
下地処理不足などの施工ミス
施工時の不手際が原因で膨れが発生することもあります。
下地の清掃が不十分でホコリやゴミ、油分などが残っていると、ウレタン防水材が下地にうまく接着しません。
また、下地と防水材の接着性を高めるプライマーの塗布量が不足している場合も、部分的に接着が弱くなり膨れの原因となります。
こうした施工ミスによる膨れは、施工後の早い段階で現れることもあります。
原因に合った補修方法を選ばなければ再発するため、原因究明が補修の近道です。
ウレタン防水のDIYでの補修が危険な理由

「ウレタン防水の膨れくらいなら自分でできそう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、DIYでの補修にはリスクが伴い、かえって状況を悪化させて結果的に余計な費用がかかることにもなりかねません。
主な理由は以下の5つです。
- 根本原因の特定が難しい
- 適切な材料・工法を選ぶのに知識が必要になる
- 被害を拡大させる恐れがある
- 高所作業に危険が伴う
- 補修工事に保証がつかない
これらの理由から、ウレタン防水の膨れ補修はDIYを避け、防水工事の専門業者に依頼するのがおすすめです。
専門業者であれば、正確な原因診断に基づいた適切な施工が期待でき、結果として建物の資産価値を守ることにもつながります。
ウレタン防水の膨れを未然に防ぐための予防策とメンテナンス

ウレタン防水の膨れに対処することも大切ですが、膨れが発生しないように予防することが、長期的に建物を守るうえで肝心です。
そのためには、適切な予防策と定期的なメンテナンスが欠かせません。
ここでは、ウレタン防水の膨れを未然に防ぐための方法をご紹介します。
湿気を逃がす「通気緩衝工法」を採用する
防水工事の改修を計画する際には、「通気緩衝(つうきかんしょう)工法」を検討しましょう。
この工法は、コンクリートなどの下地とウレタン防水層の間に、意図的に空気の通り道(通気層)を設けるものです。
下地から発生した湿気(水蒸気)は、この通気層を通って「脱気筒(だっきとう)」と呼ばれる専用の排気口から外部へ自然に排出されます。
これにより、湿気が防水層の下に閉じ込められて膨れを引き起こすのを防げます。
施工費用については、下地に直接防水材を塗る「接着工法」に比べて高くなります。
しかし、膨れの発生リスクを低減し、防水層の耐久性を高める効果が期待できるため、長期的にはコストを抑えやすい工法です。
業者による点検を受ける
建物の防水性能を長く維持するためには、専門業者による定期的な点検が有効です。
一般的には5年〜10年に一度の点検が目安ですが、建物の立地条件や使用状況によって最適な頻度は変わります。
屋上に上がり、防水層の劣化・膨れの兆候・雨水を排水するドレン(排水口)の状態などをチェックします。
もし問題が見つかっても、早期の段階であれば比較的小さな補修で済むことが多いです。
雨漏りなどのトラブルや、大規模修繕工事に至る前に対処できる可能性が高まります。
定期的に清掃などのメンテナンスをする
特に大切なのが、屋上のドレン周りの清掃です。
落ち葉や土砂、ゴミなどがドレンに詰まると、雨水がスムーズに流れなくなり、屋上に水たまりができやすくなります。
水たまりは、防水層に常に水が触れている状態になり、劣化を早める原因となります。
年に1〜2回を目安に定期的にドレン周りをチェックし、詰まりの原因となるものを取り除いて、水はけの良い状態を保ちましょう。
信頼できる防水専門業者を見抜く方法

ウレタン防水の膨れ補修を依頼する際、どの業者を選ぶのかが工事の成功を左右するポイントです。
後悔しないためにも、信頼できる専門業者を見極める必要があります。
以下の点に注目して、慎重に比較検討しましょう。
- 豊富な施工実績と専門資格があるか
- 丁寧な現地調査とわかりやすい原因・工法を説明してくれるか
- 詳細の見積書を提示してくれるか
- 保証制度とアフターフォローが充実しているか
また、複数の業者を比較する“相見積もり”をとって比較するのもおすすめです。
ウレタン防水の膨れを発見したら、まずは専門家へ相談

ウレタン防水の膨れは単なる見た目の問題ではなく、防水機能が低下しているサインです。
放置すれば雨漏りを引き起こし、結果的に建物の寿命を縮め、将来的に大きな修繕費用がかかることにもなりかねません。
防水工事に関する確かな知識と経験を持つ専門業者に連絡をとり、現状を見てもらうことから始めましょう。
ご紹介した内容が、ウレタン防水の膨れ補修に役立てば幸いです。
関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。
当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計190社の正会員がおります(2025年4月時点)。
また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。
「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。
当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。